
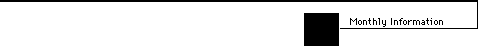
王子:北とぴあ・さくらホール 18:30
演奏者
Dir ジョエル・コーネン、ボストン・カメラータ
トリスタン: ジョン・フリーグル
イズー: アンヌ・アゼマ
ブランガーヌ:リン・トーグローヴ
マルク王: ポール・ガトリー
語り: アンドレーア・フォン・ラム
というのも、そもそも音楽の感動を文章で伝えるという行為そのものが、 読者がかつて似たような経験をどこかでしたことがあることを 前提としているのではないかと考えているからであり、 このコンサートのようにかつて出会ったことのない音楽体験から起こる感動を 文章で伝えること自体が不可能ではないかと感じるからである。
と言っていても始まらないので、 コンサートの内容について書き進めることにする。
まず、この「トリスタンとイズー」というコンサートの プログラム内容であるが、これはそういう曲目がもとから あるわけではない。12世紀のヨーロッパで大流行した 恋物語であるトリスタン伝説を著した3種類のテクストを自由に抜粋して朗読し、 その間に12〜14世紀の音楽をちりばめて再構成した独自の舞台音楽である。 そのちりばめた音楽の中にはトリスタン伝説と直接は関係ない曲も多く、 それどころかテクストと音楽を勝手に組み合わせた、 いわゆる「替え歌」すらも交えるという大胆な試みが行われている。
素材はすべて中世からとられており、楽器もその時代のものを使っていながら、 このプログラムはいわゆるオーセンティック(正統的)なものでは全くない。 これはコーエンのイマジネーションとファンタジーによって構成された 完全に現代の作品である。 そしてこの作品には観衆のイマジネーションをもかきたてる力があった。
このプログラムは海外では舞台上演も行っているらしいが、 今回は日本公演のための演奏会バージョンでの上演であった。 とは言え、そこは芸達者揃いのボストン・カメラータ。演奏会形式とは言っても そこには「極度に抽象化された舞台劇」が展開されていた。
通常のステージから客席に張り出した舞台を設置し、 演奏者はその張り出し舞台上に半円上に並べられた椅子に座っており、 テクストを朗読する語り手がその左隣りに一人で椅子に座っている。 歌手は自分の出番では立ち上がって、極度に切り詰められた演技を 伴って演奏をする。
もちろん舞台装置などは一切無く、演出と呼べるのは照明の変化と 歌手の演技のみであるのだが、これにときどきハッとするような効果がある。 例えば、イズーとブランガーヌの役は共に最初は処女として登場する。 これを象徴的に現すのが演奏の初めから羽織っている上着で、 それぞれが初めて男性と関係を持つシーンで、羽織っていた上着を取る という演出があったのだが、これなどは見ていてドキリとする ような効果があった。
また、追放されたトリスタンが狂人のふりをしてボロをまとって 再びイズーの前に現れるシーンでも、 最初は笑っていたイズーが、だんだん相手がトリスタンであるという ことに気付いていく様子を描く演技などは非常に繊細で、 とてもこれを「演奏会」と呼ぶ気にはなれなくなった。
もちろん、構成や演奏の全てがパーフェクトだったわけではない。 たとえば前半のラストを飾る 《Alle psallite cum luya》 などは、前半の最後に盛り上がりを持たせるためにとってつけた ような印象がぬぐえなかったし、 トリスタン役のジョン・フリーグルはやや技量不足、 イズー役のアンヌ・アゼマもコンディションが今一つという感じの歌唱であった。
しかしそういう批判が野暮と感じるほど、今回のステージには魅力があった。 ラストのイズーの死に際しての歌ではおもわず涙が込み上げるほどの感動があり、 まさに今回のコピー「想像力は時間を越える」に偽りはなかったと言っていいだろう。
(宮内)
四谷:紀尾井ホール 18:30
演奏者
Cd,Cm ウィリアム・クリスティ、レザール・フロリサン
S ソフィー・ダヌマン、ゲール・メカリー
Ms マリースル・ヴィクゾレク
T ジャン=ポール・フシェクール、マルク・パドモア
B ローラン・ナオリ、ベルナルド・デルトレ
ナレーター;ハリエット・ウォルター
作曲家シャルパンティエと詩人モリエールによるこの作品は、 3幕からなる演劇に序幕と即興オペラと3つの幕間劇を交えての作品で、 実際に音楽がついているのは本筋ではない序幕と即興オペラと幕間劇の方である。 シャルパンティエはイタリアの影響を受けたフランスの作曲家だけに 音楽には両方の特徴が兼ね備えられており、他のフランス作曲とは少し趣を異にする 独自の魅力があるが、この作品にはその魅力が十分備わっているといえるだろう。
序幕と第1の幕間劇にはイタリア色が強く、特に第1の幕間劇は 役者が仮面をつけて演じるコンメディア・デッラルテの形式で 演じられ(期せずしてこの日放送された「東京の夏音楽祭95」での 「マドリガル・コメディ」を思い出した人も多かっただろう)、 その一方で即興オペラや第2の幕間劇のフランス語の語りのリズムを活かした 旋律は、紛れもないフランスバロックのものである。 レザール・フロリサンの演奏はそれらの様式を捉えた好演であった。
演奏そのものに関して言うと、まずとにかくうまい。 コンサートマスターであるヒロ・クロサキが まとめる器楽アンサンブルもうまいが、歌手陣が全員うまい。 これだけ歌手がいると普通は1人や2人は落ちる歌手がいるものだが、 揃いも揃って全員うまい。この歌手たちを全員クリスティが育てたのかと 思うとこれは驚異としか言いようがない。特にメカリーの高い技術と フシェクールの個性が印象的であったが、それ以外の歌手たちも皆、 技術と個性を兼ね備えた優れた歌手たちばかりだった。
とはいえレザール・フロリサンの演奏は技術ばかりではない。 香り高いフランス語の歌唱、聴くだけで笑い出すおふざけ的演奏、 どれをとってもこの高い技術に支えられた上でのものではあるが、 またそれだけで出来るものでもなく、この団体の奥深さを感じさせた。
しかし今回の上演には2つ不満がある。一つは字幕である。 確かに英語はフランス語よりはいくぶん分かりやすいとはいえ、 やはりついていけないところもある。終始楽しむためには字幕は欲しいところだった。 もう一つは舞踏である。演奏会形式ということで舞踏は一切無かったわけだが、 それではやはり少し寂しい。せめて2人くらいダンサーを連れてきて、 舞踏を取り入れて欲しかった。
特に字幕はその気になればすぐ出来るものだけにぜひ入れてほしかった。
(宮内)
レザール・フロリサンの紀尾井ホールにおける公演「病は気から」を聴いた。 筆者はこの手のジャンルについてあれこれ言える立場にはないが、 まずはとても楽しめる演奏会だったということを報告したいと思う。 特に歌手陣の充実度はかなりの物で、個人技としてのソロの場面だけでなく、 合唱の場面でも、まるで訓練された合唱団のような楽しいアンサンブル を聞かせた。歌手陣はひとり(マルク・パドモア)をのぞいで全員が聞いた ことのない名前であったが(それはもちろん筆者が知らないだけである)、 今後、これらの歌手が出ている演奏会があれば、それだけでも期待してしまい そうなほどである。なかでもソプラノのメカリーの歌のチャーミングさ、 ハイ・テナーのフシェクールのコミカルな表現が魅力的だったことは 記憶にとどめておきたいと思う。アンコールはパーセルの曲から数曲で(もう ひとつの公演プログラムであったパーセルのステージからのものだろうか)、 これもたいへん楽しめた。
紀尾井ホールは決して広いホールではない。その真ん中よりやや後 ろの位置で聴いた。声楽に関してはまったく問題がなかったが(いい 位置だったと思う)、特にリュートなどの大きな音が出ない楽器の音 が埋もれて届いてこないことが多かったのがやや残念だった。
さて、これは、決して安い演奏会ではなかったし(S席 12,000円)、バロック 時代のオペラ、それも演奏会形式での上演、ということで、チケット を買うのにはややギャンブルめいた思いきりを必要とする演奏会だっ たかも知れない(むろん、人によっては買わずにはいられない物だろうが)。 しかしながら、舞台芸術は、その場に居合わせないと決して体験で きない物であり、会場に行かなければ得ることのできない、あとから 取り返せない物と言えると思う。そういった意味で、この演奏会は、 行くことにして本当によかった、あたりだった、と思えた演奏会だった。
(奥野)
桜木町:神奈川県立音楽堂 19:00
演奏者
Cd フルヴィオ・ラムピ
Cho カントーリ・グレゴリアーニ(グレゴリアン・チャント)
聲明 天台聲明音律研究会
さて、かんじんの演奏の方。この日前半のステージをつとめたのは グレゴリオ聖歌の「カントーリ・グレゴリアーニ」。筆者はグレゴ リオ聖歌の様式や美について語れる立場ではないが、淡泊な演奏の ように思われ、また、「この会場では彼らも歌いにくいのでは」と も思われた。教会の景色、教会の響きがあれば、もっといいだろう に、と感じた。単に筆者の耳が、エコーだらけのグレゴリオ聖歌の 録音に慣らされてしまっているだけかも知れない。
休憩後は天台聲明音律研究会による聲明である。休憩中に舞台は それらしく赤い毛氈などでセッテイングされ、香炉で香がたかれた。 休憩中だというのに、それだけですっかりムード満点、さっきまでの ムード一掃である。このステージでは、約30分ほどの全体を通じて、 客席で物音がたてられないほどの集中力のあるステージを展開した。 各自があまりテンポをそろえる事なく声を出し、その重なりやずれ が不思議な音響を作り、独特の世界を作っていた。非常に楽しめる ステージであった。
アンコールは、グレゴリオ聖歌 のAgnus Deiと聲明をいっしょに歌う、という趣向だったが、聲明が 完全に場を圧倒していたように思う。
この日の演奏は、どちらも、平和を祈っての、本物の儀式、法要として 行なわれた。特に聲明では、結婚式で聞く祝詞のような、日本人なら だれでも聞きとれることばで平和祈願のことばがささげられた。
エンターテイメントとして、ショウとしての完成度がどうこういう 種類の舞台ではなく、本物のもつ力、本物の自信を感じた演奏会 だった。それでもやはりグレゴリオ聖歌の方は演奏会のように感じ られ、聲明の方は儀式として感じられたのは、私が日本人だからな のかも知れない。
(奥野)