
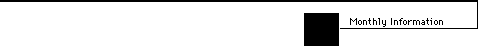
スタンフォード大学 メモリアルチャペル 20:00〜21:30
曲目 トマス タリス Loquebantur varlis linguis Sancte Deus ウィリアム ムンディ In aeternum Adolescentulus sum ergo O lord the maker など全10曲
演奏者 Cd ピーター・フィリップス Cho タリス・スコラーズ
最初に指揮者のピーターフィリップスの軽い挨拶ではじまり、 一曲目のタリスから普段通りの彼らの響きの中に包まれた。彼らの演奏を 教会で聴いたのが今回がはじめてであったが、ハーモニーのバランスは教会で その感覚を培ったに違いないと確信できるほど完璧なものであった。 今回ようやくピーターフィリップスがハーモニーのブレンドの重要性を 強調する理由を読み取れたように思われたし、 実際彼のバランス感覚が非常にすぐれていることが理解できた。
それぞれの曲の出来は普段と変わり無く思えたが、前回のこの団の イギリスもので経験したことであるが、ウィリアム ムンディの In aeternum と いう難曲は、良く頑張ってはいるものの練習不足のために合わせることに 注力されその曲の本来もつ味わいを出すまでの表現力が皆無であった。 名曲を紹介するという点ではその努力を認める部分があるものの、 あの演奏では一般の人がその曲を好きにはなれない。
ラストから2番目に1曲だけアンセムが挟まれたが、今まで経験したことがない ラテン語の曲と英語の曲との明確なコントラストがあり、これは英語を 母国語とし宗教を同じくするものという感覚が無意識 (いや意識的かも知れない)に働いているように思われた。
総じてこの演奏会は彼らの演奏としてはとても標準的なものであったと 思われるが、教会という場所、商業主義的なものの一切を排除するという 環境の違い(観客の持っている文化のバックグラウンドの違いも 作用している)が音楽へ与える影響の大きさを改めて実感した。
(新郷)
津田ホール
曲目 オーランド・ギボンズ 6声のファンタジア第3番 エルヴィス・コステロ かたづけよ、禁断の玩具* ヘンリー・パーセル ファンタジア第8番 タン・ドゥン 沈みゆく慕情* バリィ・ガイ バズ オーランド・ギボンズ 主よ、われを責めたもうなかれ* ギャヴィン・ブライアーズ イン・ノミネ ジョージ・ベンジャミン 静寂の上を* ウィリアム・ローズ 6声のパヴァンとエア マイケル・ナイマン イナンナの自己とその全能を誉め讃える歌*
演奏者 Vn CO フレットワーク CT マイケル・チャンス(*印曲のみ)
マイケル・チャンスの歌唱を聞くのは録音も含めてこの日が はじめてだったが、この日は必ずしも好調とは言えなかったようだ。 とにかく音程がふらふらしておちつかない。 これがいつものことなのかこの日に限ったことなのかはわからない。
曲はどちらかというと現代の物の方が魅力的に聞こえた。前半では、 タン・ドゥンの、効果音のような発声やポルタメントを多用した不思議な 雰囲気を持った作品が面白く、後半では最後を飾った マイケル・ナイマンの作品に力が入っていたようだ (映画「プロスペローの本」の劇中歌のようなパターンの曲)。
このコンサートで特に印象に残ったのはアンコールの最後で歌われた バードの曲。マイケル・チャンスの独唱で始まったが、後半になって フレットワークの6人も楽器を弾きながら合唱しはじめ (アドリブというわけでなく、そういう曲らしい)、感動的な効果をあげていた。
(奥野)
バリオホール
マショー、バタイユ、ダウランド、カッチーニ、モンテヴェルディなどの 歌曲とリュートのソロを数曲
演奏者 Lu つのだたかし S 波多野睦美
リュートは普通のホールだと(小ホールといわれるホールでも) 音が届きにくいとよく感じるのだが、このホールは最後列でも ステージの音がよくつたわり、よい選択だったと思う。
波多野睦美の歌は、おそらく「いつも通り」のことなのだろうが、 表現豊かな、そして端正で美しいものだった。伴奏ともほとんど一体と いっていい状態で、これといった合図もなく、淡々と歌い進む。 そういう意味では静かなステージだったが、歌の表現は多彩で、 いろいろな表情を聞くことができた。
前半に歌われたP.Guedron(1623-58)の「どんな希望が持てるのだろう」と、 最後を飾ったC.Monteverdi(1567-1643)の「さらばローマよ」が印象に残った。 特に後者は強い声を使ったダイナミックな表現がされていて迫力があった。 強い声を出していても、なお自然で心地よい、無理のない印象を与える ところがさすがといったところか。
(奥野)