
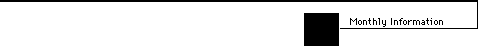
客層は、なぜか、4〜50代あたりと思われる夫婦でつれそっ てきている客が目についた。どういったわけだろう。普通の 合唱のコンサートとも、古楽系のコンサートとも、なんだか 違った客層だった。
前回の公演同様、ステージには黒い布をかけた長テーブルをおき、それを囲む かたちで5人の歌手とリュート奏者が座った。曲間にリュート伴奏をはさみな がら、時にはメドレー風に歌いつないでいく趣向。
はじめのうちはやや不安定なアンサンブルもみせていたが、たいして心配する までもなく立ち直り、終わってみれば見事な演奏会であった。
とにかくカウンターテノールのドミニク・ヴィスの表現が目立つが、テノール のブルーノ・ボテルフもなかなかいい味を出しているし、ベース系の安定感も 高い。前回来日時とはメンバーが変わっていたベースを歌ったアントワーヌ・ シコも重厚な低音を鳴らしていた(彼は何となくポール・ヒリヤーを若くした ような風貌)。
このアンサンブルの魅力はいろいろあると思うのだけど、私 は何といっても、下品すれすれ、いや、時には下品そのもの といってもいいくらいに生き生きとして調子にのった音楽表 情・表現が彼らの持ち味だと思う。このスタイルを確立した 現在、このアンサンブルはまさにのりにのっていると思える。 このスタイルは今後は「クレマン・ジャヌカン・アンサンブ ル風」に聞こえてしまうわけで、彼らの「芸風」は、一流の アーティストがもっている武器「オリジナリティ」を示 すものだろうと思う。
現在聞くことのできる、世俗曲を歌うアンサンブルとしては(いささかクセは あるものの、いや、それだからこそ)一級品の、聞き逃せない魅力をもったグ ループといえるだろう。このアンサンブルの演奏を聞いて「ああ、こんなのも ありなんだ」と、それまで思いもしなかったようなアイデアをつかんだ人も少 なくないのではないだろうか。
この日演奏された曲目は極めて世俗的(パンフレットの日本語訳を作られた方 もいささか苦労した部分もあったかも知れない)な内容の曲が多く、ホールで じっと座って静かに聞く種類の音楽ではないように思われた。彼らも舞台上か らにやにやしながら歌っているようだった。こういうのはばか騒ぎの中でぐちゃ ぐちゃになって歌う種類の音楽なのかも知れない。この曲たちを日本語に訳し て講習の面前で歌うのはちょっとヘビーだと感じる人は少なくないだろうと思 う。
アンコールではお得意のクレマン・ジャヌカンの「狩り」などが演奏され、そ の表現の豊かさを思う存分にまき散らし、圧巻だった。
音楽を、そして、特に合唱を演奏する側の人間には非常に刺激的な演奏会だっ
たと言えると思う。そして、つねづね思うのだが、このようなコンサートが、
決して安くはない(S席7000円)とはいえ、居ながらにして聞けるという東京近
郊の環境はありがたいものだ。その分いろいろ面倒なことがあるにしても、な
かなか離れられない都市である。
(奥野)
客席は9割程度の入りだろうか。クレマン・ジャヌカン・アンサンブルのカザ ルスホールでの初日よりわずかに多いか、というあたり。比較的女性が多めで ある。「ドミニク・ヴィス・フアンクラブ」の勧誘チラシがあったりして、な んだか妙な感じだ。なお、ドミニク・ヴィス・フアンクラブは、このコンサート を後援していた。
さて、ドミニク・ヴィスといえば、一度聞いたら忘れられないとでも言おうか、 必ずしも美声とは言い切れないが何とも言えない独特の声と、その思いきった 表現、とくにコミカルな味が魅力だと思う。この日もおなじみの声で歌ってい たのだが、中低音の安定度がどうもいまひとつだったようだ。カザルスの残響 もなんだか妙な感じで(D列16番あたりの席で聴いた)柔らかい弱音の発声の響 きが独特の残響になり、違和感があった。ホールのせいではないのかも知れな いが。
クレマン・ジャヌカン・アンサンブルの公演と同じく、リュートの伴奏にのっ て歌い、曲間にリュート独奏曲をはさんだりしながら、時にはメドレーのよう な形でルネッサンス期の世俗歌曲を歌っていった。ダウランドなどの英語の曲、 カッチーニなどのイタリア語の曲、そして母国語フランスの曲と歌われていっ たのだが、ヴィスの歌はどうも英語やイタリア語に聞こえない。そしてフラン ス語の曲になると見違えるように表現が豊かになるような気がする。やはり母 国語だと気持ちのノリが違うのだろうか。フランスの曲が次々と歌われた後半 のステージに、表現のおもしろいものが多かった。
総じてレベルは非常に高かったと思うのだが、いまいち燃焼感に欠けるコンサー トだったと思う。なぜだろう。あまり変化がなかったからだろうか。
アンコールでは、ヴィスのリサイタルの別プログラムから、ラヴェルの曲など
が歌われた。個人的にはいきなりそういう曲が出て来てやや違和感があったが、
曲としては楽しめた。考えようによっては「毛色の違う曲も聞けてラッキー」
とも言えるだろう。
(奥野)