
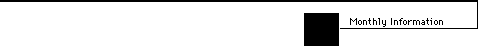
四谷:聖イグナチオ教会 19:00
曲目 ・中世フランスのクリスマス 「今日キリストは生まれたまいぬ」 「祝いの日が来たりぬ」 「アレルヤ、と賛歌を歌え」 「パティパタパン」他 ・ドイツの祝福の歌 「来れ、羊飼いたちよ」 「今日こそは声高く」他 ・イギリスの古いキャロル 「マリアのひざに眠るこの子は?」 「天の女王よ、祝福を受けたまえ」他 ・スペインの聖母マリア賛歌 「母なるマリアよ」 「器楽によるカンティガス」 「聖母マリアを深く愛し」他
演奏者 Dir,Lu つのだたかし S 波多野睦美 R,Shwm 江崎浩司 Fid 田崎瑞博 Perc,Dlcim 近藤郁夫 ゲスト CT 米良美一 Vg デヴィット・ハッチャー
コンサートはフランス、ドイツ、イギリス、スペインの順に 各国の古いクリスマス曲を集めた4部構成でプログラミングされ、 器楽奏者は全員いくつかの楽器を持ち換えながらの演奏で、 全体を貫く雰囲気は保ちながらも ヴァラエティに富んだ演奏が繰り広げられた。
この団体は過去に木島千夏、牧野正人といった歌手たちとも 共演を行っており、その歌手陣の充実ぶりには定評があるところであるが、 今回の歌手もソプラノの波多野睦美とカウンターテナーの米良美一という 何とも豪華な顔合わせで行われた。
この2人の歌のうまさ、表現力の豊かさはいつものながらに 素晴らしいしたものであった。特に波多野睦美は、 その歌唱力もさることながら自ら曲の世界に入り込む役者のような演奏で、 聴衆をもその世界に取り込むことのできる貴重な歌手であると感じる。
しかしこの日のコンサートはそういった個々の要素よりも、 コンサート全体の雰囲気のトータル性が際立っていた。
やや寒さを感じる薄暗い教会の中、ほのかに浮かび上がる祭壇、 その中で歌われる中世のクリスマスの歌、 深い表現をたたえた演奏、そして教会の残響。
会場そのものの持つ雰囲気と、演奏される曲目、その演奏内容が 見事に一致した素晴らしいコンサートであった。 「やはりこういう曲はこういう風に演奏されなくては」とすら感じる、 曲本来の魅力を十分に引き出したコンサートと言っていいだろう。
そして最後は観衆全員を巻き込んでの全体演奏(音取りは 波多野睦美指導でその場で行われた)で締めくくり。 終演後、駅へ向かう人々の中からは、最後の全体演奏で歌った曲を 口ずさんでいるのが漏れ聴こえる。
「レコード芸術」誌で特選に推薦されるなど、その演奏のレヴェルの 高さには十分定評のある団体でありながら、単なる高水準の演奏に留まらない こういうコンサートを企画するあたりは、さすがつのだたかしと 言ったところだろうか。
(宮内)
三軒茶屋:昭和女子大学 人見記念講堂 17:30
演奏者
Cd 大谷 研二(3rd, 4th)、林 順治(1st)、小島 誠(2nd)
Orch 東京室内管弦楽団(4th)
S 大谷 しほ子(4th)
FP 山部 陽子(2nd)
Cho 東京工業大学混声合唱団コール・クライネス
(ただしカッコ内は出演ステージを表す)
ここ十年来のコール・クライネスをよく知る筆者が、まず全体を通して 一番強く感じたことは、アマチュアにありがちな(時として不愉快にさえ なってしまう程の)「甘え」をほぼ脱してきたということだ。 何より聴衆が音程を気遣うようなばかげたことは、(後述の第 3ステージを 除けば)ほとんどなくなっていたと思う。このレベルに達していれば、 内輪でない者にお金を払ってもらい金額分(自由席 1,000円)は十分に 満足させられる演奏会だったと思う。実際、17:30 という早い開演時間にも かかわらず、初めから一階席は 8割以上埋まり、縁故者が義理で来る 割合が以前に比べてかなり低くなっているような印象を受けた。
第 1ステージ - 黒人霊歌集
(「Keep in the Middle of the Road」、
「Tone Duh Bell Easy」、「Good-Bye, I'm Goin' Home」)
この日のステージの中では、最もやさしいと思われる曲目で、
ともすると適当に和音が響いて適当にまとまって聴こえてしまいがちになる
ものを、正確なピッチとていねいな発音で丹念に歌い込んだことに、
大変好感が持てた。難しくない曲にこそ合唱団の実力が
問われるのだとしたら、このステージから
コンクール金賞受賞が偶然の産物ではないと感じさせてくれた。
第 2ステージ - 萩原 英彦:混声合唱組曲「白い木馬」
このステージの良し悪しは、筆者にはよく分からなかった。
ただ、大学合唱団では「耳休め」的ステージになりがちな学生指揮者の
ステージで、単なる漠然とした音取りには終わっていないように
感じた。唯一のピアノ伴奏付きステージであったが、
この曲の(筆者が勝手に考えた)持ち味である、
ピアノと合唱のかけ合いが、特に女声部は良く表現できていたと思う。
第 3ステージ - 祈りの音楽
(Thomas Tallis「Spem in alium」、
John Tavener「Let Not The Prince Be Silent」)
筆者はこのステージに演奏前は一番期待を寄せていた。
プログラムからも客演指揮者:大谷 研二の
並々ならぬ意欲を感じたのだが、本番は驚くほど低調であった。
何と 2曲めは譜持ちだったことからも明らかなように、
ひどい練習不足だったと聴き初めてすぐに分かった。
大学合唱団としては本邦初演であったのだが、
新たなものを紹介しようとするせっかくの取り組みもこれでは台無しだ。
どちらも多群合唱で、コール・クライネスの(200人近い)大人数という持ち味を
本当ならば生かせる作品であったはずなのに、歌詞不明瞭・音程不安では
メリハリのあるステレオ効果も出せず、返すがえすも残念であった。
あり得ないことながら、あと 1か月くらい
練習を積んだ彼らを、再び聴いてみたいと感じてしまった。
第 4ステージ - John Rutter「REQUIEM」
前ステージの物足りなさを、出だしから一気に解消してくれた。
ほとんどこちらばかり練習していたのではないかと疑いたくなるほど、
見違えるような、記念演奏会をしめくくるにふさわしい名演だったと思う。
第 1ステージで感じられた曲作りへの積極さが、最後に戻ってきた。
筆者は作曲者自らが録音したこの曲の CD を聴いたことがあるのだが、
何だかつまらない曲だ、という感じが全くの誤解であったことを
気がつかせてくれたコール・クライネスの一同に心から感謝したい。
最後に、新たに常任指揮者となる大谷 研二と、 初のオケ付きステージを成功させたコール・クライネスの、 現在のレベル、すなわち前 常任指揮者:加藤 磐郎が築いてきた 音楽レベルに飽き足りない更なる発展を心より期待しつつ、評を終える。
(吉村)