
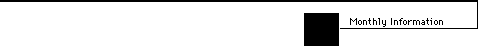
曲目
ヴィラールト 「1550年の詩篇」より
「新音楽」より
G.ガブリエーリ「サクラ・シンフォニア集(1597)」より
「カンツォンとソナタ集」より
「サクラ・シンフォニア集(1615)」より
演奏者
Cd.エリク・ファン・ネーフェル
器楽Ens.コンチェルト・パラティーノ
Cho.クレンデ・アンサンブル
Org.ヘルマン・スティンダース
16世紀中頃のヴェネツィアでの2重合唱曲の誕生は、「対比の原理」 の上に成り立つと言われるバロック音楽の幕開けとなる出来事である。 そのためこれらの曲は音楽史上重要な意味を持つのであるが、 これまで録音が少なく聞かれる機会もあまりなかった。
そういった状況の中で新しく発売されたこのCDは、 演奏の技術レヴェルも非常に高く貴重なディスクといえるだろう。 特にコルネットの透明で独特な響きは他の楽器で再現できるものではないので、 これらの曲を本来の楽器で聴けるというのは嬉しい限りである。
合唱団のレヴェルも高く、ヴィブラートのない正確な 音程が金管特有の純正な響きと良く溶け合って 美しいハーモニーを聴くことができる。 ただ欲を言えば、もう少し演奏に華やかさと躍動感が あったほうが良かった気がする。
ともあれこのCDの演奏は、これら貴重なレパートリーを知る
スタンダードな演奏として評価できるものであろう。
(宮内)
曲目 パルティータ イ長調(原曲:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ3番 ホ長調 BWV1006) パルティータ ト短調(原曲:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ2番 ニ短調 BWV1004) パルティータ ホ短調(原曲:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ1番 ロ短調 BWV1002) 演奏者 Cm グスタフ・レオンハルト
また、バッハの曲を知りつくしたレオンハルトによる編曲を 彼独特のアーティキュレーションで聴くと、 どちらが原曲か分からなくなるような箇所さえある。 これもレオンハルトならではのことであろう。
このレパートリーは、現代ヴァイオリンの巨匠たちの演奏には 解釈に疑問のある演奏が多く、またS.クイケンによる バロック・ヴァイオリンの演奏は技術レヴェルに難があるため、 決定版といえるディスクはまだないように思う。
その中にあって、このレオンハルトの演奏やビルスマの チェロ・ピッコロによる演奏、ノースのリュートによる演奏が 高い評価を得ているが、これもバロック・ヴァイオリニストによる 真の名演がないからではないだろうか。
そんなことを考えてしまう一枚だった。
(宮内)